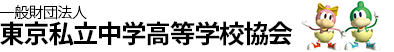【研究所ブログ第58回】研究協力学校(桐朋女子中・高等学校)「発表会」のお誘い
令和7年5月17日(土)、 研究協力学校(桐朋女子中・高等学校)「発表会」が開催されます。テーマは「過程に寄り添うT-Projectの学びを通して生徒が身につける力」です。
詳しくは→https://k.tokyoshigaku.com/seminar/school/partner46.html
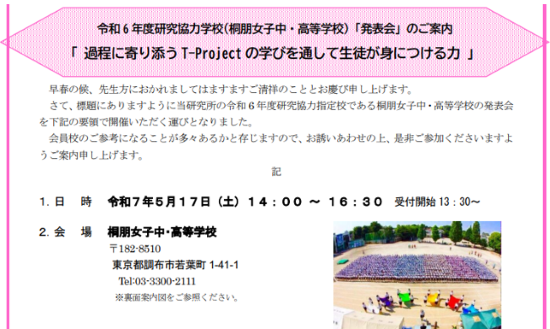
発表内容については、実施案内に詳しいので、そのまま引用します。
「桐朋女子では、2022年度から高等学校1年生全員が受講するT-Projectが始まった。T-Projectとは、桐朋女子のProject-Based Learning(以下、プロジェクト型探究という)の意味を込めて、当時の準備委員会が提案し、その他の候補の中から教員の投票によって選ばれた名称である。桐朋女子では、2022年度から高等学校1年生の総合的な探究の時間に加え、2024年度からは中学校3年生の総合的な学習の時間にT-Projectを実施している。
本研究では、この3年間の実践を通して、過程に寄り添うT-Projectを通して生徒がどのような力を身につけることができるのかを明らかにする。過程に寄り添うのは、アドバイザーとしての教員だけではなく、生徒のプロジェクト型探究に関わる周囲の生徒や専門家、地域の人々である。生徒を取り巻くこれらの人々がどのように生徒の学びの過程に寄り添うのか、また、それにより学びの主体である生徒がどのような力を身につけるのかを明らかにする。
そして、T-Projectが、知識・技能の習得や思考力、判断力、表現力の育成を重視するプログラム型探究ではなく、この2つのコンピテンシーに加え、どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るかという学びに向かう力、人間性を育成する新たな学び、つまり、生徒主体のプロジェクト型探究となっているのかを検証する。」
今回の同校の研究は、独自のT-Projectの実践研究の背景に、デューイやその弟子であるキルパトリックの理論や日本PBL研究所のエドビジョン型プロジェクト型学習及びそのモデルの発祥となるミネソタ・ニューカントリースクールに関する論文などまで幅広くリサーチされています。
すなわち、今回の研究発表では過程に寄り添うT-Projectの学びを通して生徒がどのような力を身につけるのかその実践的検証のみならず、その理論的背景にまで及ぶ包括的な研究内容が発表されると予想されます。
令和6年度「教務運営に関するアンケート結果報告書」によると、東京の私立学校234校のうち20.9%が全学的にアクティブラーニングを実施し、ほとんどの教科、学年で実施している学校が16.2%を占めています。特定の教科や学年によっては実施しているという学校は21.8%です。これらを合わせると、58.9%ととなり、アクティブラーニングに対し高い関心があることがわかります。
T-Projectとアクティブラーニングは同じものではありませんが、主体的・対話的で深い学びを追究している先生方にとっては、大変参考になる研究です。ぜひご参加していただき、いっしょに生徒の成長をサポートする学びの環境を考える機会にしていただけると幸いです。