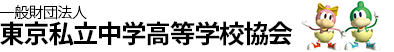【研究所ブログ第48回】合理的配慮を学び、心理的安全性を確保
令和7年2月21日(金)、教務運営研究会は「講演会・情報交換会」を開催します。テーマは、「学びを深めるための心理的安全性の確保」です。
詳しくは→https://k.tokyoshigaku.com/seminar/kyomu/s-school%20affairs23.html

(教務運営研究会の夏合宿のシーン)
2024年度から私立学校にも合理的配慮が求められるようになりました。教務運営研究会では、夏期宿泊研修会でもテーマの1つとして取り上げ、まず法令的な考え方を学び、私たちのできることは何か、できないことは何か等の理解を進めてきました。
この合理的配慮は、現状では、入学時において、互いに理解を深めるコミュニケーションの重要性について議論されることが多いのですが、今後は、学級経営や教育相談といった場面でも、教師と生徒の理解や意識、価値観の違いについて互いに理解するときに、とても重要な基準になります。
しかし、その基準は、かなり複合的に構成されているために、生徒のためを思ってコミュニケーションをとったと思っても、理解の行き違いを生んでしまうことがあります。平田オリザさんも語るように、みんな違うことは大切ですが、そのうえで、互いに理解を深めることはとても難しいことなのです。合理的配慮は、そこに挑戦する覚悟と言い換えることができるかもしれません。
合理的配慮は、多くの場合、特定の状況における「気持ち」「行為」「考え方」の全てが組み合わさったものと考えられています。
➊気持ち:他者を理解し、共感する姿勢が必要です。相手の立場やニーズを理解しようとする気持ちが大切です。
➋行為:具体的な支援や環境の整備が必要です。例えば、段差をなくしたり、適切なコミュニケーション方法を提供したりすることです。
➍考え方:全体的なアプローチやマインドセットも重要です。包括的な社会を目指し、差別やバリアをなくすための意識を持つことが求められます。
つまり、合理的配慮はこれら全ての要素が調和して初めて成り立つものですから、具体的な状況においてこれらをどのように融合させていけばよいのか日ごろから学び、そして振り返りができるようにしていく必要があります。しかし、その共有や蓄積の機会はあまりありません。
そこで、本研究会では「学びを深めるための心理的安全性の確保」というテーマで、講演会・情報交換会を企画しました。合理的配慮が行われる授業や面談の仕組みをいっしょに作っていきましょう。