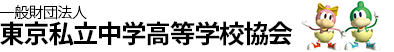【研究所ブログ第26回】絶望を希望に変える教務の仕事
この夏、教務運営研究会は5年ぶりに「2泊3日の宿泊研修~教務の仕事の再発見と新発見」を実施します。

詳しくは→https://k.tokyoshigaku.com/seminar/kyomu/8136.html
今多くの学校が、昨年5月にコロナ感染症が5類になり、特別な対応はほぼなくなったものの、コロナ禍で変化したことに対応する「アフターコロナ」の時期をいかに過ごすか苦慮しています。
また、学習指導要領改訂に伴う新教育課程の編成、大学入試改革への対応、ICT活用の推進など、教育の大きな変化への対応も求められ、教務部の先生方に膨大な業務が覆いかぶさってきています。
さらに、教師不足は、授業運営に大きなダメージを与え、それを修復するために、教務は日々奔走しています。
この時代の大きな変わり目に生まれた歪みは、とても、独りで責任を負い乗り切れるものではありません。私立学校の教員がお互いに知恵を出し合い、行動していく必要があります。そこで、同運営研究会は、「教務の仕事の再発見と新発見」というテーマで二つの視点を取り入れた研修会を企画しました。
初日は東京大学 大学総合教育研究センターの栗田佳代子先生を講師にお招きし、「ティーチング・ポートフォリオ(TP)」のワークショップを行います。実際にTP作成の振り返りのプロセスをTPチャートというワークシートに取り組んでいきます。
2日目には、おにざわ法律事務所の鬼澤秀昌先生より合理的配慮について法律的な観点から講演を依頼しました。4月から私立学校にも合理的配慮が義務づけられ、経営陣や事務局だけではなく、教員も手探りで対応していると推察します。合理的配慮を進めていく上で留意すべき点など、事例をもとに講演していただきます。
この2つのセミナーをきっかけに、分科会を通して教務的課題について多角的に情報交換の時間を設けています。
本当に、学校の周りには、信じられないリスクが存在し、そのリスクを学校の経営陣は、常にマネジメントして学校の評判や教職員の生活を守る努力をし続けています。
ところが、昨今は、心理的な危機が、日常の学校生活のコミュニケーションの中で起こるリスクが頻発しています。
かつては、行事や部活でケガなどの事故のリスクをマネジメントすることに重点がおかれていましたが、ある重大ないじめの事件がきっかけで、教師と教師、教師と生徒、生徒と生徒、教師と保護者など学校内のコミュニケーションの状況によっては、意識せずにハラスメントが起きているケースを防止する対策が必要になってきました。
授業の中や面談の中で自分一人では、良かれと思っている言動が、実は相手に不快な思いをさせ、ハラスメントに発展するリスクがあると気づけない状況が増えてきたのです。それゆえ、仲間同士、あるいは外部のスタッフも交えてリフレクションという対話をする機会が重要になってきたのです。
授業は認知能力だけではなく非認知能力も育まなければ、そのようなアンコンシャスバイアスを払しょくできない教育の時代になったのです。
そこで、授業改善及びコミュニケーション改善などの側面から、新しい教務の在り方について対話する研修を実施することになりました。リスクマネジメントは経営陣だけの役割ではなく、現場で豊かなコミュニケーションをとる教師の身近なリスクマネジメントも必要になってきたのです。
そのようなリスクを回避することによって、互いの心が疲弊するのを防ぎ、学校の評判を作ることに寄与し、訴訟など法的トラブルを回避することができるようになるでしょう。何より、トラブルに対する多大な精神的疲弊や学校のネガティブな評判を回復するには、強靭でタフな精神力と莫大な費用を要します。そうならないように、適切な対応をしていかなければ、リスクが怖くて新しい教育にチャレンジできないという生徒にとっても教師自身にとっても絶望的な状況が生まれます。
ですから、この絶望を希望に変えるには、現場の教務力にかかっているといっても過言ではありません。この夏、教務の在り方の再発見と新発見をじっくり語り合いましょう。