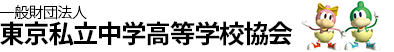【研究所ブログ第22回】英語の「実践研究」という新次元
令和6年6月28日(金)アルカディア市ヶ谷(私学会館)で、文系教科研究会(外国語)は、「研修会:実践研究入門 ―実践の理解と改善のために―」を開催します。
◆詳しくは→https://k.tokyoshigaku.com/seminar/bunkei/post-1953.html
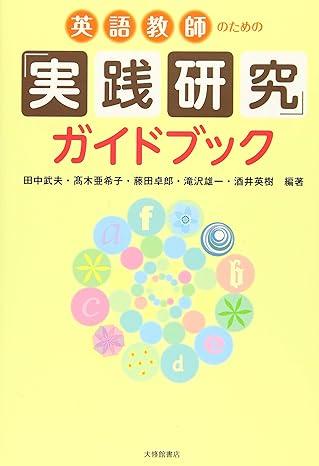
1960年代から1970年代にかけて、アクション・リサーチという「実践研究」が始まりました。この手法は、教育現場での実践を通じて問題解決や改善を目指す手法であり、教育者自身が主体的に研究を行うことを重視しています。
戦後、社会学や心理学が、実際の集団と個人の関係に注目し、一人一人の幸せと社会の幸せのジレンマをリサーチし、解決する方法を追究しました。その方法の一つとして、この「実践研究」は開発されました。
この「実践研究」と対照的な方法が「実践報告」です。
「実践研究」が量的研究と質的研究の両方を活用するのに対して、「実践報告」は何をどのようにやったか、すると成果はどうなったのか、その量的研究が中心でした。
ところが、国語や英語など言語能力を育成する学びは、どうしても「対話」的にならざるを得ず、そのプロセスは、量的研究では見えない部分が多数ありました。そこで、質的研究の開発が進んだのです。
これにより、教師と生徒のかかわりを多面的に議論し、その改善の方法に気づく研究の道が開かれたのです。
近年小学校に外国語活動が導入され、高学年の外国語科が設置されました。また、大学入試の英語にも4技能化が徐々に進んでいます。さらに生成AIなど英語の授業にDX化の波も押し寄せています。そのような時代の流れがあるにもかかわらず、日本の15歳は学力的にはトップクラスですが、英語の運用力は弱いとされています。
そのため、近年、英語の授業方法について改善していくことが期待されているのです。そして、英語の授業の改善を促進するために、すでに多くの領域で効果を生み出している「実践研究」が活用される機会が多くなりました。
そこで、今回の研修では、長年の言語教師教育の実績を有する青山学院大学教授の髙木亜希子先生をお招きし、授業改善に活用できる「実践研究」の手法を紹介していただきます。研修会では授業における悩み事に関するディスカッションを行った上で、問題の本質に迫り、授業改善につながるテーマを発見するグループワークも行う予定です。
委員の先生方は、「今後の中高の教育現場で活かせるように、表面的ではない解決策を共有したい」という想いを抱いています。