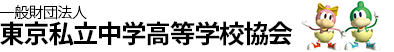【研究所ブログ第24回】探究と修学旅行の統合化時代

令和6年6月13日(木)、アルカディア市ヶ谷(私学会館)で、プロジェクト部会「グローバル社会とこれからの平和教育」は、<「実践報告会」~事前・事後学習を核とした修学旅行の探究的展開~>を開催しました。
同プロジェクト部会は、パンデミックの期間中に新学習指導要領に移行したこともあり、それ以降、修学旅行のアプローチは変化していることに注目しました。新学習指導要領の流れは、社会全体が、多様で複合的なグローバルリスクに直面している社会課題をいかに解決するかその探究的な学びに期待がかかっています。
私立学校は、その建学の精神に基づいて、もともと社会課題やその痛みを引き受けてその解決のために貢献するリーダーを育成することを目的にしています。
その在り方はグローバルリーダーだったり、サーバントリーダーだったり、コミュニティーシップ型リーダーだったり、私学の建学の精神によって様々ですが、社会リスクに立ち臨み、世界の痛みを共有して世界を好転させる知恵と勇気と行動の資質・能力を育てることにおいては共通しています。
したがって、今回のパンデミックを体験することによって、修学旅行も今まで以上に生徒たちの探究心を刺激し、社会や世界に開かれた視点を育む貴重な学習機会として再構築されています。多くの学校の先生方もその新たな挑戦に試行錯誤を重ねていますから、先進的な修学旅行のデザインとその実践による効果について共有したいという想いは高まっています。
そこで、本研修会では、「実践報告会:事前・事後学習を核とした探究的アプローチ」をテーマに掲げ、2名の先生から実践報告を発表していただきました。
郁文館高等学校の都築敏史先生は「課題解決型」探究旅行を実施しており、生徒一人ひとりが選んだ学問を通じて地域課題を解決する取り組みについて共有していただきました。
また、晃華学園中学校高等学校の安東峰雄先生は、修学旅行を探究学習の集大成と位置づけ、様々な課題に取り組んでいる事例を紹介していただきました。
郁文館の試みは、修学旅行にいたるまで、多様なPBLを学内外とネットワークをつなぎながら行っていく体験を積み上げていくという、壮大なプランニングがデザインされていました。その過程で、生徒が徐々に教師の手から離れ、主体的にプランニングから外部連携の交渉などをするようになる姿に、参加された先生方は刺激を受けました。
晃華学園の試みも、あらゆる教育活動の中に「書く行為」を核に探究を埋め込み、その深い教養を身につけていく圧巻のプログラムが前提にありました。修学旅行をその集大成として昇華させていく先生方の教育デザイン力にやはり参加者は刺激を受けました。
プレゼン終了後、このような探究と修学旅行を結び付けた事例を通して、参加した先生方が気づいたことをシェアしました。そして最後に各グループごとプレゼンをしました。その後2名の先生から、フィードバックをもらうことができました。
その参加者の気づきを、次の5つの項目に分類して整理してみました。
A:探究と修学旅行の統合
・探究学習と修学旅行を組み合わせることで、生徒が主体的に学びを深める機会を提供できます。
・修学旅行を通じて、現地でしか見られないものや会えない人、できないことを体験させ、対話的な学びを促します。
・修学旅行の目的地を「連れて行きたい場所」から選ぶことで、生徒の興味を引き、探究的な思考力を養います。
B:事前・事後学習の時間確保
・修学旅行の前後に学習の時間を確保することは重要です。
・事前学習では調べ学習を通じて問いや課題を準備するだけではなく、こまめにリフレクションや中間報告をします。事後学習ではまとめや発表を行います。
・アポイントを取り、取材のマナーや受け答えを学習することで、生徒が現地で効果的に活動できるようサポートします。
C:修学旅行のプラン作成と主体性
・生徒自身が修学旅行のプランを作成することで、主体性を高めます。
・プロジェクト型のアプローチを取り、生徒が目的地や活動内容を決定することが重要です。
・生徒の変化を観察し、修学旅行の経験が進路指導やキャリア教育にどのように寄与するかを理解することが大切です。
D:修学旅行のプランを決定する体制
・修学旅行のプラン作成は、管理職や学年団との協力を通じてトップダウン型またはプロジェクト型で行うことができます。どのアプローチを選ぶかは学校全体の体制の見直しとも関連しています。
E:生徒の変化のイメージを明快に想定
・修学旅行を体験する前と後では、生徒がこのように変わると想定してプランを作ったり、生徒自身がプランをつくれる環境をデザインすることが重要です。