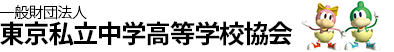【研究所ブログ第23回】教科横断的学びの多様な取り組みと課題を共有
令和6年6月6日(木)アルカディア市ヶ谷(私学会館)で、プロジェクト部会は研修≪「教科横断への道」~「深い学び」を実現するための「教科横断」へのアプローチ~≫を実施しました。

『教科横断』的な学びは、学習指導要領の改訂を受けて、『主体的・対話的で深い学び』の実現に伴い、カリキュラム・マネジメントの重要な学びのプログラムとなっています。複合的な社会課題に直面している生徒たちが将来社会で活躍するために必要なマインドとスキルを育成する上で、一つの鍵となる可能性もまた議論されています。
一方で、この『教科横断』を検討していく際には、その導入時のみならず、継続していくにも、さまざまな課題が存在し、悩みを抱えている先生方が多いのも事実です。そこで今回、授業やカリキュラムの研究をされている、東京大学大学院教育学研究科の藤江康彦教授に講演をお願いしました。教科横断の学びが、資質・能力を育成するのに重要な役割を果たすことを期待している文部科学省の基本的な考え方とそれを受けて実践している幾つかの学校の事例報告をしていただきました。
その後、グループワークを通じて、参加者同士が情報を共有し、互いに学び合う時間を50分ほどとりました。自由闊達で熱い参加者の情報交換の様子から、いかに私学の先生方が教科横断の学びを重視しているかがわかります。
最後に各チームごと情報交換した内容をプレゼンし共有しました。その内容を次の3点に分けて整理しました。教科横断の学びの課題が出尽くしている感があります。発表の中にもありましたが、やれない理由を言っていないで、パッションをもって進んでいこうという気概を共有できた研修となりました。
教科横断型の授業について、以下の3つに分類してみました。
- 難しさ:
- 教科横断は先生同士の協力が必要であり、調整や計画が複雑です。
- 属人的なプログラムは持続可能性に欠けることがあります。
- 評価方法の選定も難しい課題です。
- 創意工夫しているケース:
- 平和共生論文のプログラムなど、特定のテーマに焦点を当てた教科同士による横断型授業があります。
- 数学と保健体育の組み合わせでは、データサイエンス的な視点で保健の内容を考えています。
- 興味関心があるものを扱えば、おのずと教科横断型になります。
- 今後の重要なポイント:
- 教科横断型授業をカリキュラム内または外で実施するかの選択が課題です。
- 各校や先生の事例を共有し、ベストプラクティスを探求することが重要です。
- 大学入試の変化に対応するため、柔軟なアプローチが求められます。
- 教科横断は多くのブリッジを作成し、それを統合する必要があります。